コラム
月経と女性のからだ

女性のからだと月経は、生涯を通して切り離せない関係にあります。月経は単に「毎月くるもの」ではなく、ホルモンの変動に合わせて心身にさまざまな影響を与える、生理的でとてもダイナミックな現象です。そのため、月経周期に関連して不調を感じる方も少なくありません。
■ 月経後〜排卵までの約14日間:からだが軽く感じやすい時期
月経が終わると、卵巣では次の排卵に向けて卵胞が育ち始めます。この時期はエストロゲン(卵胞ホルモン)が徐々に増えるため、心身の調子が比較的安定しやすいといわれています。
- 気分が前向きになりやすい
- 肌の調子が整いやすい
- 体が軽く感じ、活動しやすい
■ 排卵後〜次の月経までの約14日間:子宮内膜が厚くなる時期
排卵が終わると、プロゲステロン(黄体ホルモン)が優位になります。このホルモンは妊娠に備えて子宮内膜をふかふかに厚くする働きを持っています。
しかし同時に、
- 体がむくみやすい
- 気分が落ち込みやすい
- 眠気やだるさが出やすい
など、心身に負担を感じる人も増える時期です。いわゆるPMS(月経前症候群)の症状が現れるのもこのタイミングです。
■ 子宮内膜が剥がれ落ちるとき:月経と痛みのメカニズム
妊娠が成立しなかった場合、厚くなった子宮内膜は役目を終え、体外へ排出されます。これが月経です。
このとき、子宮は内膜を押し出すために収縮します。収縮そのものは自然な働きですが、収縮が強すぎると痛みとして感じられます。
- 下腹部の痛み
- 腰の重だるさ
- 下肢の鈍痛
など、いわゆる「生理痛」と呼ばれる症状がここで起こります。
収縮が過剰になる原因は冷えやホルモンバランスの変化などありますが、漢方の世界では子宮の過剰な収縮を和らげる方法・冷えが強い方は温めならが血の巡りを良くする方法など様々です。
生理痛にお悩みの方はお一人お一人の体質にあった漢方薬をお選びしますので、お気軽にご相談ください。
喉に関するご相談

最近、喉に関するご相談が増えております。
〇喉に突然違和感がでて咳が出始めた。咳は止まったが声が枯れて出なくなってしまった。
〇コロナにかかったが3週間たっても咳だけ取れない
といったお悩みが増えております。
暑さの影響も大きいかと思います。
痰といっても、痰の状態を詳しく伺い体の状態をさぐっていきます。
また、日中と夜との寒暖差の影響で風邪をひきやすい時期でもあります。
夜寝る時は真夏のような恰好は控えて身体を冷やし過ぎないようお気をつけくだい。
軽い頭痛、喉の痛みなど風邪の初期症状が出た時は早めの漢方薬がオススメです。
プロテインは善か?悪か?

プロテインとは、「タンパク質」のことで、筋肉・臓器・皮膚・髪・爪・ホルモンなど、人間の体を構成する主要な栄養素です。サプリメントとしてのプロテインは、タンパク質を効率よく補うための栄養補助食品として広く使われています。
プロテインに関する誤解が多く、正しい知識をもって自分にはプロテインが必要かどうかを判断していってください。
〇プロテインの役割
- 筋肉の修復・成長を助ける
- 肌・髪・爪の健康を保つ
- 免疫力や代謝の維持に関与
- ダイエット中の筋肉減少を防ぐ
〇こんな人におすすめ
・ 筋トレやスポーツをしている人
・ダイエット中で栄養不足が心配な人
・食事だけで十分なたんぱく質が摂れない人
食の細い方や食べても太れないような方が手軽に栄養を補給するといった点で正しく摂取すればメリットは十分にあると感じています。美容効果や栄養バランスの補助といった目的では必要かもしれません。
しかし、間違った摂り方をすると体を壊しかねないので注意が必要です。
〇プロテインの過剰摂取による注意点
タンパク質を摂取すると、体内で代謝されて尿素窒素(BUN)やクレアチニンなどの老廃物が発生します。これらの老廃物は、腎臓でろ過されて尿として排泄されます。
つまり、タンパク質の代謝=腎臓の仕事が増えるということになります。
なので、必要量以上にプロテインを摂ると腎臓の負担を高めてしまい、腎臓の機能低下(悪化)につながりやすくなるので注意が必要です。
ある文献には、体重1kgあたり2.0g以下のタンパク質摂取であれば、腎臓への負担は極めて低いとする研究もあります。
※プロテインで太る可能性があるケース
1. カロリーオーバー
・プロテイン1杯あたりのカロリーは約70〜180kcal。
・食事で十分な栄養を摂っているのに、さらにプロテインを追加すると余剰カロリーが脂肪として蓄積されることがあります。
2. タンパク質の過剰摂
・タンパク質は筋肉の材料ですが、使われなかった分は脂肪に変換される可能性があります。
※よくあるプロテインの勘違い
1. 飲めば筋肉がつく
プロテインはあくまで「材料」。筋肉をつけるには筋トレなどの刺激が必要です。飲むだけでは筋肉は増えません。
2. プロテインを飲むと痩せる
痩せるかどうかは摂取カロリーと消費カロリーのバランス次第。
プロテインを摂ることは良いことばかりではありません。
ご自分の体調を見ながら必要かどうかを判断していってください。
「夏バテ・熱中症」の予防

今年も暑い夏がやってきました。
夏バテ・熱中症を心配して対策されてる方も多いかと思います。
今回は夏バテ・熱中症を予防するためのお話しをしたいと思います。
まず、夏バテとは…
夏の暑さにより「体がだるい」「食欲がでない」「疲れやすい」といった症状をいいます。
一般的に夏バテを予防するには規則正しい生活やバランスのとれた食事、適度な運動習慣が大切と言われています。
【夏バテ・熱中症になりやすくなるポイント】
1.汗のかき過ぎ・水分不足
こちらは一般的に言われてることで、最も注意が必要ですね。最近の猛暑により汗をかきすぎて具合が悪くなったり、水分を取らなさすぎて体の水分が奪われて体調を崩すケースも多いです。
2.冷房に当たり過ぎ
最近はどの施設でもエアコンは完備されていますし、スーパーは寒いくらいに冷房が効いています。現代人の意識の変化からか、過度に冷房を効かせすぎている感じもします。特に「汗をかく=暑い」→設定温度を下げるや、暑い人に設定温度を合わせ寒いと感じる人は上に羽織るという感じもします。
3.体の冷やしすぎ
夏も体の冷えには注意が必要です。2の冷房の当たり過ぎもありますが、冷たい飲み物の摂りすぎで体の中を冷やしすぎて胃腸機能が麻痺して消化不良・食欲不振に陥るケースもあります。
現代は自販機も充実しておりどこでも冷たい飲み物が手に入る時代となりました。また、飲み物には氷を入れる方も多いですが、これも夏バテの一因となってしまいます。
また冷たいビールも美味しい季節ですが飲みすぎには注意です。
4.水分の摂りすぎ
よく「熱中症予防に水分はしっかり摂ってます」と言われる方は多いですが、反って水分の摂りすぎが体調を崩す原因にもなりかねません。
中には毎日2L飲むように心がけてると言われる方もおられます。しかし、人の体はそれぞれ強さ弱さがあります。汗かきな人や外仕事が多い人は2Lの水分が必要かもしれません。しかし、2L飲んでも大丈夫な人もいれば、2Lも飲んで体調を崩す人もいます。
これはその人その人の胃腸の強さによります。胃腸が体に入った水分を上手に排出してくれたら良いのですが胃腸の弱い方が2Lもの水分を摂ると体に水分を貯めこみ浮腫みやめまいの原因となってしまいます。
【夏バテ・熱中症対策】
バランスのとれた食事
といっても難しく考えることはありません。が、食事を簡単に済ませる方が多いように感じます。特に暑くなるとそうめんやうどんで済ます方も多いのではないでしょうか?
食事は一汁三菜とまではいかなくてもタンパク質(肉・魚)を摂るように心がけましょう。またお味噌汁は飲む点滴と言われるほど体に良いので、夏バテ・熱中症には効果的です。
水分の摂り方
お水・お茶をしっかり摂ってるから大丈夫と思われてる方が多いですが、お水やお茶はさほど吸収はされません。
なので、熱中症になった方もお水・お茶をしっかり摂ってたと言われる方は多いです。
やはり、吸収の良い飲み物はOS-1(経口補水液)やスポーツドリングですが、スポーツドリングは糖分が多いのも心配です。
夏の間、毎日飲んでたら秋に糖尿病を発症してしまったと言われる方もおられました。
オススメは果物や野菜を摂ることです。(オススメの果物や野菜は下部参照)
適度な運動
適度に汗をかくことは夏バテ対策に有効です。
逆に汗をかきすぎると脱水状態になってしまうので、早朝や夕方の少し涼しい時間帯に軽くウォーキングを取り入れるのがおすすめです。
また、朝・晩はエアコンは入れずに外の風を取り入れて自然の風を感じるのもオススメです。肌の表面に軽く汗ばむのを心地よく感じるようになるでしょう。
<夏バテ・熱中症にこそオススメなのは夏野菜や果物>
飽食の現代、お腹を満たすことは簡単になりました。しかし、食事の内容に気を使わなくなってるように感じます。
おやつ1つとっても、昔はお菓子の種類も少なく、きゅうりやトマトをおやつに食べていた記憶もあります。
かたや、最近は熱中症対策として「塩分チャージ」という商品がでてきました。発汗によって失われた体内の塩分(ナトリウム)ミネラル(カリウム)を素早く補給するというものです。とても画期的な商品で味や種類も豊富にあります。
現代っ子は「エブチャ食べよー」とおやつの1つとして常備する時代になりました。手軽に口にできる分、怖さも感じております。
手軽さコスパの良さから、果物や野菜は後回しになっているのではないでしょうか?
夏バテ・熱中症予防にこそ果物や野菜が必要と感じております。
果物や野菜は水分・ビタミン・ミネラルも豊富に含まれているので毎日でも摂ることをオススメします。
朝、食欲ない時も何か1種類、果物を取り入れてみてください。
以下、夏の野菜・果物の主な栄養素をを載せておきます。食べる時の参考にされてください。
・レタスーβカロテン、ビタミンK、葉酸
・トマトーβカロテン、ビタミンC、リコピン
・きゅうりー95%以上が水分、βカロテン、ビタミンK・ゴーヤービタミンCが豊富、βカロテン、葉酸
・とうもろこしー野菜の中ではカロリーは高め、ビタミンE、ナイアシン、葉酸、食物繊維・スイカー90%が水分、ビタミンC、カリウム、ビタミンA
・パイナップルービタミンC、ビタミンB1、マンガン
・ぶどうークエン酸、ビタミンA、ビタミンB1,ビタミンC、ビタミンB6、カリウム
・桃ービタミンE、ビタミンC、ポリフェノール
・バナナービタミン、ミネラル、食物繊維
その体の不調、「天気」のせいかも?
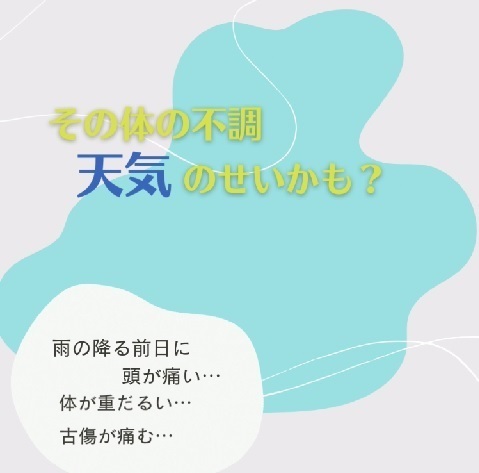
春の陽気になると体の不調を感じる方がいます。
なぜだかわからないけど、体がだるい、寝ても寝ても眠い…など。
それは、気候の変化によって起こる体の不調かもしれません。
気候の変化とは、当に気圧の変化です。
春は北の冷たい空気と南の温かい空気がぶつかって低気圧が発達しやすくなります。
この時期に使われることわざに「三寒四温」とありますが、当に上空では温かい空気と冷たい空気がぶつかり合っているために毎日の寒暖差が起こり、気圧の変化を敏感に感じ取り、体の不調へとつながっているのです。
ご相談の多い症状としては
・頭痛、片頭痛(特に雨の降る前の日に起こりやすいと言われる方が多いです)
・倦怠感(体のおもだるさ・疲れがとれない)
・めまい、立ちくらみ
・耳鳴り
・肩こり、首こり
・古傷の悪化
今までは気にならなかったのに、年齢と共にひどくなったという方や、産後ひどくなった、と言われる方もおられます。
漢方では体の中からバランスをととのえていき、不調の改善へと導くことができます。
頭痛薬が手放せないという方や、病院では異常はないと言われた方は一度ご相談ください。
漢方薬局
SALON DU KAMPOU
(サロン ド カンポウ)

住所
〒752-0975
山口県下関市長府中浜町7-10
アクセス
駐車場:近隣に提携のコインパーキングあり
受付時間
月・火・木・金 9:00~17:00
土 9:00~16:00
定休日
日・水・祝日